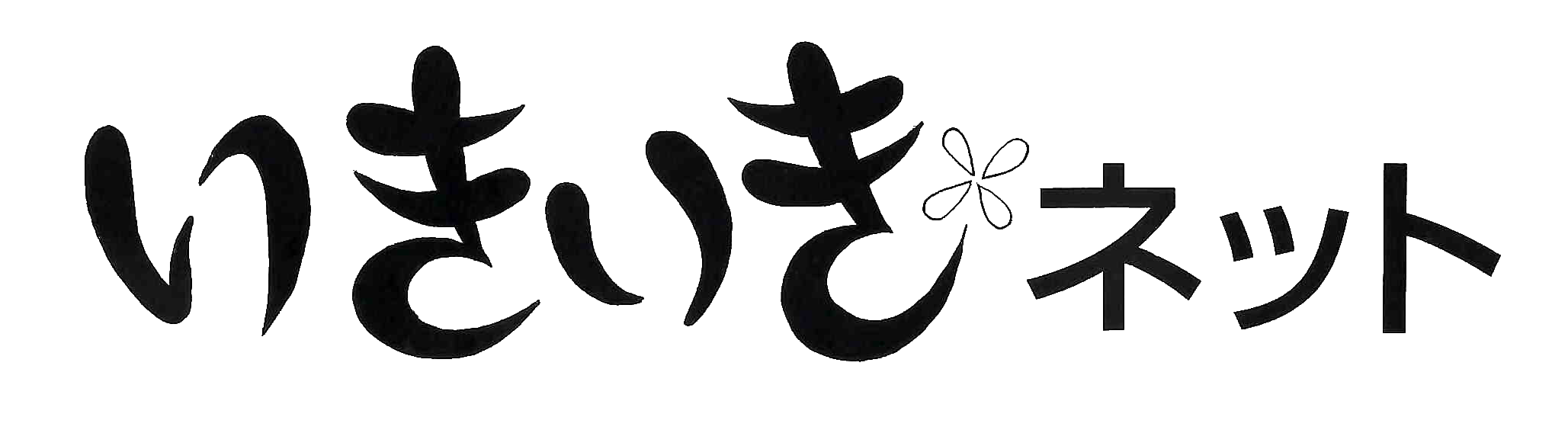1万6000年にわたって定住した三内丸山遺跡
世界には無数の遺跡がいまだに深い地中に埋もれている。それが私達の目に入るのは、建物を建てる為の土木工事で発見されたり、山を歩いて偶然探し当てたとかもあったりする。このシリーズでは、その発見のドラマや普遍的な事実を追及しながら「遺跡を歩く」旅を皆様と追っていければと考えている。
遺跡発見の歴史
縄文時代は1万数千年という長い期間である。縄文文化は狩猟採集だけの文化と違うということが、理解されるきっかけとなる遺跡が、三内丸山遺跡といって良い。近隣と交流する秀でた文化を有していたのである。
この遺跡は江戸時代から知られてはいたが、昭和になってから発掘調査が行われ始め、平成に入り、1500年に渡り続いた遺跡である事が判明してきた。平成7年より施設整備が進められ、遺跡の公開も始まり、2000年(平成12年)に特別史跡に指定された。縄文遺跡では3例目の指定。
発見のドラマは明らかでないが、江戸時代の山崎立朴著『永禄日記(館野越本)』の元和9(1623)年正月二日の条に次の記述が残っている。「又青森近在之三内村二小川有此川より出候瀬戸物大小共二皆人形二御座候、是等も訳知不申候」とある。
縄文時代のイメージを払拭した遺跡
縄文時代というと、私は教室の後ろに張り出されていた歴史マップを思い出す。毛皮を着て槍を持ち、狩猟する姿から原始人のイメージしかなかった。ところが、最近の発掘の成果からすぐれた文化と争いのない共同社会であったことが判明してきている。
三内丸山遺跡は縄文時代前期(BC5500年)から中期(BC4000年)にかけて生活した場所。この時期は縄文文化が最も栄えた。それを写真から見ていこう。
豊富なクリやクルミなどの実を保存。その際、土器(写真①)が使用された。狩りには槍の先につける石として黒曜石(写真③)が使われた。他の地域との交流がうかがわれるヒスイの大珠(写真④)や漆の付着した土器(写真⑤)。着飾っていた女性が想像できる装身具(写真⑥)。祈りの際に使われたのではと思われる板状土偶(写真⑦)。自然の恵みに感謝しながら、自給自足の生活をし共同社会として平和な定住生活が1500年続いたことは驚異的なことだ。